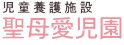沿革
聖母愛児園の始まりは、一般病院(中区山手町82)の玄関先に子どもが放置されていた昭和21年4月です。その後、駅や道路に置き去りにされている乳児を警察がシスター達のところへ連れてくるようになり、聖母病院からも同じような乳児が届けられました。シスター達は、一般病院(中区山手町82)内で、子どもたちの養育を始めました。
昭和20年代30年代は、ドイツ・カナダ・ハンガリア・ポーランド・イングランド等のシスター達も活躍していました。
昭和21年8月までに、子どもたちを22名預かり、翌年8月までには136名受け入れるなど、献身的に働きました。昭和20年代は戦後の混乱期であり、生後間もない子どもたちが放置されており、その上、発疹チフス、痘そう・コレラ等の伝染病が蔓延していました。預かっても疾病や栄養失調等で死亡に至るケースが多く、献身的に働く職員たちの心中は、穏やかではなかったことでしょう。
また、昭和25年から昭和35年までは、アメリカのご家庭との養子縁組があり250組程の縁組みが成立していました。
以下、沿革の概略を記します。
■1946年(昭和21年)4月
病院の玄関先に子どもが置き去りにされていた。病院の一角を利用して、収容、保護にあたった。
■1946年(昭和21年)4月
病院内で2歳まで預かり、その後カトリックの施設に移すつもりで保護事業を創立した。
■1946年(昭和21年)5月31日
ルルドのマリア様のご保護の許に、創立年月日とする。
■1946年(昭和21年)9月
現在地の山手町68番地に乳児院を新設、名称を聖母愛児園として独立。
*OUR LADY OF LOURRDES BABY HOME(ルルドの聖母ベビーホーム)
■ 1946年(昭和21年)10月
生活保護法の施行により「救護法」失効
■1948年(昭和23年)1月1日
児童福祉法制定施行:「孤児院」⇒「養護施設」
■1946年(昭和21年)8月15日
5月から22名預かり、12名は他のカトリック施設に移る。現在10名在籍
■1947年(昭和22年)8月15日
この1年間に136名受け入れる。40名死亡、17名は他の施設に移る。現在79名在籍
■1948年(昭和23年)8月15日
この1年間に243名受け入れる。50名死亡、32名は本会の他の施設に移る。現在161名在籍
■1949年(昭和24年)8月15日
この1年間に233名受け入れる。17名死亡、51名は他の施設に移る。現在165名在籍
■1950年(昭和25年)8月15日
この1年間に215名受け入れる。8名死亡、10名北広島の本会の施設に移り32名は他の施設または養子として引き取られる。現在165名在籍(3歳以下120名、3歳以上45名)
■1951年(昭和26年)8月15日
この1年間に235名受け入れる。7名死亡、22名カトリックの家庭に引き取られる。現在206名在籍(3歳以下151名、3歳以上55名)
■1952年(昭和27年)8月15日
この1年間に185名受け入れる。2名死亡、31名アメリカのカトリックの家庭に引き取られる。現在152名在籍
■1953年(昭和28年)8月15日
この1年間に171名受け入れる。2名死亡、33名アメリカの家庭に引き取られる。現在136名在籍
■1954年(昭和29年)8月15日
この1年間に195名受け入れる。2名死亡、42名アメリカの家庭に引き取られる。14名家族の許に帰る。現在137名在籍
■1955年(昭和30年)8月15日
この1年間233名受け入れる。55名カトリック家庭へ引き取られ、41名は少年の町(Boys Town)へ受け入れられ、19名は母親の許へ帰る。2名死亡現在116名在籍
■1956年(昭和31年)8月15日
この1年間に196名受け入れる。2名死亡、49名アメリカの家庭に引き取られる。28名母親の許へ帰る。現在117名在籍
■1955年(昭和30年)
横浜聖母愛児園分園「ファチマの聖母少年の町」落成。聖母愛児園より34名の男児が移る。
*1971年(昭和46年)閉鎖。アフターケア施設ヨゼフ寮として存続。
■1956年(昭和31年)
Baby Home(現聖母愛児園)と修道院の建築着工。翌年竣工。
鉄筋コンクリート、地下1階地上3階建築
地下:厨房、洗濯場アイロン室、乾燥室、倉庫
1階:乳幼児室、応接室、事務所
2階:3歳から10歳までの女子の子供室
3階:修道院
建築費用:47,054,440円
■1960年(昭和35年)
アメリカへの養子縁組終了。
■1965年(昭和40年)8月
鉄筋コンクリート3階建(新館)着工。翌年5月竣工。
■1970年(昭和45年)10月
災害に備えて、避難階段、すべり台、バルコニーを増設、窓サッシの一部改修、厨房工事、職員倉庫の新築。
■1974年(昭和49年)3月
学童風呂場改修工事着工。49年7月完成。
■1977年(昭和52年)3月
幼児減少のため乳児部を閉鎖。
■1987年(昭和62年)
外壁塗装及び大型乾燥機交換
■1996年(平成8年)
耐震診断実施、耐震補強より建て直しが最善との結果
■1998年(平成10年)
児童福祉法改正施行 「養護施設」⇒「児童養護施設」
■2001年(平成13年)8月
「社会福祉法人基督教児童福祉会広安愛児園」を「社会福祉法人キリスト教児童福祉会」へ変更
■2001年(平成13年)
分園型自活訓練事業、本郷ホーム開始。翌年10月地域小規模児童養護施設として認可。
■2003年(平成15年)
児童棟を一部改装。14名1グループにし、グループ毎に食堂を整え居室も大部屋から2~3人部屋とした。
■2005年(平成17年)10月
「社会福祉法人聖母会」から「社会福祉法人キリスト教児童福祉会」へ法人移管
譲渡条件
●希望退職者を除く職員全員を継承する。
●土地・建物は現状のまま無償譲渡し事業を継承する。
●土地・建物運用財産の明細は省略します。
*聖母会が土地・建物を無償譲渡することによりキリスト教の精神を維持する。
■2007年(平成19年)11月
現建物着工。
鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板ぶき3階建て 児童養護施設
鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板ぶき3階建て 児童養護施設
鉄筋コンクリート造陸屋根4階建て 児童養護施設
鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板ぶき3階建て 職員宿舎
延べ床面積 3,769.46㎡
居室数と居室形態 5LDK=12ホーム、低年齢児ホーム
1人部屋(洋室6畳程度*全居室数の6割)、2人部屋(和室6畳程度)
敷地面積 5,240.98㎡(1,588坪)
■2010年(平成22年)8月
現建物竣工。
■2010年(平成22年)9月1日
本園定員70名から90名へ
■2011年(平成23年)10月
児童家庭支援センターみなと開所
■2024年(令和6年)
地域小規模児童養護施設千代崎ホーム開所
地域小規模児童養護施設 本郷ホーム沿革
平成12年(2000)年 社会福祉法人 聖母会より、社会福祉法人 キリスト教児童福祉会へ、児童養護施設 聖母愛児園の土地及び運営を移管したいとの申し出があり、その準備のため、キリスト教児童福祉会理事長 森勉が、理事長を降板し、聖母愛児園施設長に平成13(2001)年4月1日就任するとの取り決めがなされた。
平成13(2001)年1月15日 借家の賃貸開始
平成13(2001)年4月1日 本郷ホーム開始
平成13(2001)年度児童養護施設分園型自活訓練事業実施申請書 平成13年4月3日付
平成13(2001)年4月1日 児童養護施設分園型自活訓練事業の実施施設の指定 平成13年6月8日付
平成14(2002)年度地域小規模児童養護施設指定申請書 平成14年4月1日付
平成14(2002)年10月1日 地域小規模児童養護施設の指定 平成14年9月19日付
平成14(2002)年度地域小規模児童養護施設に係る保護単価 平成14年4月分から適用
平成17(2005)年10月1日 社会福祉法人 聖母会から社会福祉法人 キリスト教児童福祉会へ移管
平成25(2013)年10月2日 別借家 借家建替のため
平成26(2014)年7月1日 元の借家へ戻る
カトリック系の聖母会から、プロテスタント(ルーテル)系のキリスト教児童福祉会へ財産移管するという歴史上稀な話しが進むことにより、人事異動が生じ、理事長が降板し施設長就任とともに、地域小規模児童養護施設に従事中の職員を人事異動することになり、当時の聖母愛児園施設長が、その受入のため、地域小規模児童養護施設より申請が通りやすい児童養護施設分園型自活訓練事業の申請を進めた。同時に賃貸住宅の準備も進めた。
平成13年4月に新施設長就任とともに児童養護施設分園型自活訓練事業として本郷ホームを開設した。4月時点では、まだ、指定は受けていない状況であったが、6月時点で正式に指定を受ける。
児童養護施設分園型自活訓練事業は、地域小規模児童養護施設に向けての前段階であり、翌年の平成14年に地域小規模児童養護施設の申請を行う。指定を受けたのは、同年の10月からではあるが、措置費等の補助金は、同年4月に遡ってからの支給となった。
平成17年10月に法人移管が完了した。
賃貸住宅による地域小規模児童養護施設の運営であるが、住宅の老朽化により、耐震強度の面で子どもたちの安全を守れていない現状があり、その旨、大家さんに相談したところ、建替の話しが持ち上がった。設計の段階から関わらせていただき、工事中は、別の賃貸住宅と契約を結び仮生活とした。約9ヶ月後、竣工となり、建て替え後の賃貸住宅を利用、現在に至る。