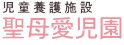聖母愛児園の理念は、単なる福祉施設の運営方針ではなく、キリスト教精神に基づいた「神の家族」としての共生と愛の実践を核としています。その理念は、戦後の混乱期に始まった人道的支援の延長線上にあり、現在も児童養護の根幹を支えています。
聖書に基づく理念の柱
「あなたがたは、もはや外国人でも寄留者でもなく、聖なる民に属する者、神の家族である」
(エフェソの信徒への手紙 第2章19節)
→ 血縁や国籍を超えて、すべての子どもを「神の家族」として受け入れる姿勢を示しています。
「わたし(キリスト)が愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい」
(ヨハネによる福音書 第13章34節)
→ 子ども同士、職員と子ども、地域社会との関係においても、愛と尊重を基本とすることを強調。
「神は愛です」
(ヨハネの手紙Ⅰ 第4章8~9節)
→ 養育の根底にあるのは、神の無償の愛であり、それを日常の支援に反映させることが理念の核心です。
理念の実践
家庭的な養育環境:
小舎制(ホーム)による家庭的なユニットを導入し、4〜6名の子どもが擬似兄弟のように暮らす。家庭的な雰囲気の中で養育。
担当職員が生活全般を支え、個別の発達段階に応じた支援を実施。
個性の尊重と素質の伸長:
一人ひとりの背景や発達段階に応じた支援計画を策定。
協力と責任の共有:
年齢に応じた役割を担いながら、互いに助け合う生活を通じて社会性を育む。
自尊心と自主性を育む養育を重視:
子どもたちの内面のケアにも力を入れています。
トラウマインフォームド・ケア
職員は研修を受け、心の傷に寄り添う姿勢を持っています。
実践的な養育方針
暴力のない環境作り:
「暴力をなくす」「いやなタッチをしない」「いってはいけない場所に行かない」「暴力を見たら大人に伝える」など、子どもと職員が共有する4つの約束を掲げる。
年3回の「みんなの集会」で再確認している。
子どもの意思尊重:
こども運営委員会や高校生会などで子どもの声を聞き、生活改善に反映。
自己決定の尊重:
支援内容の説明と同意を徹底し、子ども自身の意思を反映した支援計画を策定。
治療的ケア(トラウマインフォームド):
心の傷に配慮した養育を実施。職員は専門研修を受け、安心感のある関係性を築く。
リービングケアの導入:
小学高学年から進路や生活力について話し合いを開始。
子どもに寄り添う支援:
昭和時代における管理的な「北風の養育」から、温かく包み込む「太陽の養育」へと方針転換。
自尊心と自主性の育成:
子ども自身が「大切にされている」と感じられるような関わりを重視。
安心・安全な関係性の構築:
職員が子どもの心の傷に寄り添い、信頼関係を築くことを重視。
孤立を防ぐ自立支援:
退所後も孤独に陥らないよう、社会とのつながりを意識した支援を実施。
個別支援計画の策定:
一人ひとりの発達段階や背景に応じた支援計画を作成し、定期的に見直しを行う。
地域との交流:
地域行事や学校活動への参加を通じて、社会性と帰属意識を育む。
プライバシー保護:
年齢に応じた個室の提供、入浴・排泄時の配慮、権利擁護の話し合いを定期的に実施。
アフターケア:
自立サポートで社会的自立まで支援を継続し、卒園後も面会や訪問などの堅苦しい関わりというより「お茶する」(話し相手)支援を実施。
アフターケア施設や外部団体と連携し、就労・進学・生活支援を継続。
理念の継承と進化
設立母体の変遷:
カトリック系の聖母会から、ルーテル系のキリスト教児童福祉会へ移管(2005年)。
理念の継続:
2005年にカトリック系の聖母会から、ルーテル系のキリスト教児童福祉会へ経営移管されました。
宗派が変わっても、「神の家族」「愛と奉仕」の精神は継承されている。
養育ブックの活用:
「聖母愛児園みんなのしおり~養育ブック~」に理念と実践方法を明文化し、職員間で共有。
養育の理念・支援方法・子どもとの関わり方を体系的に記載。
聖母愛児園のキリスト教主義は、戦後の人道支援から現代の児童福祉まで、理念・実践・組織運営のすべてに貫かれた価値観として息づいています。