ファチマの聖母少年の町出身者 Dr.Riley
Dr.Riley(本名:里吉広)は1949年10月15日に神奈川県横浜市で生まれました。彼の幼少期の一時期はファチマの聖母少年の町で過ごしました。以下に日本での幼少期に関する主な情報をまとめます。
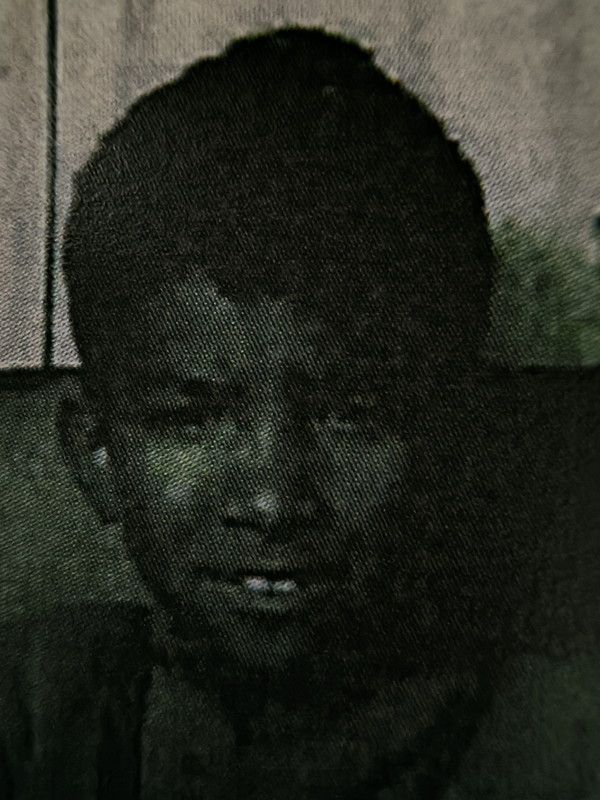
BoysTownAlbum写真を拡大
幼少期の概要
出自と家族構成
実母は日本人、実父は米軍関係のアフリカ系アメリカ人。
幼い頃に実父は家庭を離れ、ライリー博士は実母とともに日本で育ちました。
母の生活が困難となり、彼は約1年半ほど児童養護施設で暮らしました。
その後、アフリカ系アメリカ人の父と日本人の母を持つライリー家に養子として迎えられました。
言語と教育
養子に迎えられる9~10歳まで、日本語のみを話して育ちました。
養父母とともに東京郊外の立川米軍基地近くに居住し、アメリカの学校に通学し始めました。
祖父の影響
母が日中働いていたため、祖父(日本人で学校教師)と多くの時間を過ごし、教育的な影響を大きく受けた。
祖父は非常に厳格で、学校以外でも高学年向けの数学問題を解かせるなど、学習への規律を重んじました。
こうした教育方針が、後の科学者としてのライリー博士の問題解決能力と知的探究心の土台となりました。
社会的背景とアイデンティティ
児童養護施設は混血児のための施設で、東京近郊のカトリック・ミッションによって運営されていました。
当時の日本では混血児に対する差別もありましたが、彼自身は「楽しい思い出が多かった」と述べています。
自身の多民族的な背景が、世界観や価値観の形成に強く影響したと語っています。
文化的影響
子どもの頃から「科学者になりたい」と言っており、その動機の一つとして、日本の戦後復興期に読んだ未来都市や科学技術を描いた漫画や雑誌の影響がありました。
特に手塚治虫の『火の鳥』シリーズが科学や技術への関心を高めるきっかけとなりました。
米国への移行
タイ・バンコクへの移住を経て、インターナショナルスクールに通学。
高校卒業後、米国スタンフォード大学に進学するため渡米しました。
ライリー博士の日本での幼少期は、文化・言語・教育・家庭・社会の複雑な要素が交差する環境で育まれた貴重な経験でした。特に、教育熱心な祖父と多文化的な家族構成が、彼の科学への関心、公衆衛生への志、国際的な視点を養ううえで決定的な影響を与えました。
Dr. Lee W. Rileyについて
Dr. Lee W. Rileyは、感染症、疫学、公衆衛生の分野において世界的に著名な研究者です。以下に彼の主な功績をまとめます。
主な研究・科学的功績
1. 大腸菌 O157:H7 の発見
1983年、米国オレゴン州での食中毒アウトブレイクの原因として大腸菌O157:H7を同定。この発見は、後の食品安全政策や感染症対策に大きな影響を与えました。
2. 腸管病原性大腸菌(EPEC)の分子生物学的研究
スタンフォード大学のゲイリー・スクールニック研究室でのポスドク期間中に、EPECの病原性因子とプラスミド発現の関係を解明。
*この研究は、分子疫学の手法が感染症研究に応用される契機となりました。
3. 多剤耐性結核の研究
結核菌の侵襲因子や遺伝子を特定し、薬剤耐性株の分子疫学と伝播経路を明らかにする研究を展開。
Science誌に、結核菌の新規浸潤遺伝子に関する論文を発表(1993年)。
4. グローバルヘルスと都市感染症の研究
インド、ブラジル、バングラデシュなどのスラム地域で感染症の疫学研究を行い、貧困と感染症の関連性を明らかにしました。
特に都市スラムにおける結核やグラム陰性菌感染症の流行について、社会的要因と病因の交差を解明する研究を進めました。
5. ニワトリ用サルモネラ菌ワクチンの開発
公衆衛生の視点から家畜衛生にも取り組み、食品由来感染症予防のためのワクチン開発を行いました。
所属・役職
・カリフォルニア大学バークレー校 公衆衛生学部 感染症・疫学 教授
・フォガティ・インターナショナル・センター グローバルヘルスエクイティ所長
主な受賞・栄誉
・ピュー生物医科学奨学生
・コーネル大学生物医学奨学金
・ロバート・ウッド・ジョンソン財団フェロー
・マイケル・ウォルク臨床学者賞
・ジャック・フリードマン若手研究者賞
主な論文・出版物(一部)
"Hemorrhagic colitis associated with a rare Escherichia coli serotype"(NEJM, 1983)
"Cloning of a DNA fragment associated with entry and survival of Mycobacterium tuberculosis"(Science, 1993)
多数の論文が感染症ジャーナル、Science、NEJM、Clinical Microbiology Journalなどに掲載
その他の重要な貢献
感染症に対する分子疫学の導入:
病原体のDNA解析を通じて、発生源の追跡や感染ルートの特定を可能にしました。
科学と社会の橋渡し:
一般市民が科学を理解しやすくすることの重要性を強調し、教育・啓発活動にも関与。
地理医学(Geographic Medicine)プログラムの設立:
グローバルヘルスにおける先駆的アプローチ。
Dr. Rileyの功績は、単なる研究成果にとどまらず、感染症制御、公衆衛生の実践、グローバルヘルスにおける社会的公正の追求に貢献する、極めて広範かつ実践的なものである点に大きな意義があります。
2022年10月19日没、享年73歳